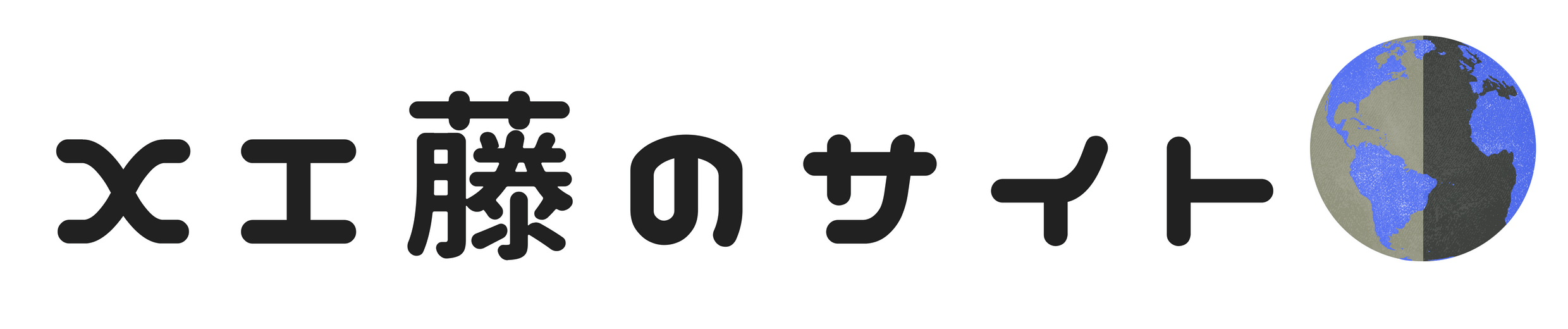前回はこちら
※続かないと言ったくせに続き書いてしまってすいません!引き続き全く意味はないので暇過ぎてティッシュで鶴とか折り始めそうとかいうレベルで暇だったら読んでください!
7月20日の午後3時13分。
樋口菜奈の携帯電話が、バッハの第九のメロディを奏でた。
別段彼女はバッハが好きな訳ではない。最初から携帯電話の設定を変えていないだけだ。
樋口は電話に出ようか迷った。着信画面には「宇佐美啓次」と出ている。
宇佐美が自分に電話を掛けてくる時は、往々にして面倒な用件だ。
それを樋口は経験から知っている。そして一度電話に出たら、例えそれがどんなに困難なものでも、自分が宇佐美の頼みを断れない事も知っている。
迷ったが、結局樋口は電話に出ることにした。この半年で二度、樋口は宇佐美からの着信を放置している。さすがに三度出ないとなれば、宇佐美から小言を聞かされるだろうと思ったからだ。
「はい、樋口です。」
「やあ樋口君。宇佐美です。最近調子はどうだい?」
「いやぁ全然です。やっぱりウチは先生の事務所のように知名度もないし、実績も乏しいですから。閑古鳥が鳴いてます。」
「おや、そうか。最近僕から電話を掛けても君が出ないものだから、てっきり引っ切り無しに依頼人が駆け込んでいるのかと思ったよ。」
失敗した、と樋口は思った。こういったやや遠まわしな言い方がいかにも宇佐美らしい。
しかしそれでも宇佐美の口調は、人を不快にさせるものではない。
「ところで、樋口君。実は樋口君に、少し頼みたい事があるんだ。」
そらきた。樋口は自分の勘の良さに満足したが、この後の展開を考えて少々憂鬱になった。
「なんでしょう?私などに先生のお手伝いができればいいのですが。」
「ハハ、大した事じゃないよ。単なる人探しだ。」
終わった…。樋口は事務所の椅子に座ったままがっくりとうなだれ、机に思い切り頭をぶつけた。
宇佐美が依頼に「単なる」をつける時は、ほぼ確実に「単なる」の領域を超えたものであるに違いないからだ。
以前に「単なる」尾行を頼まれたときは、対象者が海外を飛び回る宝石のバイヤーだったし、「単なる」浮気調査の時は、対象者がヤの人だった。
「単なる人探し…ですか。アレですか?対象者は国会議員ですか?宇宙飛行士ですか?革命家ですか?元アイドルですか?死刑囚ですか?空手マスターですか?元たのきんトリオですか?仙人ですか?トシちゃんですか?」
「どうしたんだ。落ち着きたまえ樋口君。そもそもトシちゃんに該当するものが少なくとも3つあったぞ。」
「……はあ……。わかりました。わかってます。探しますよ。先生の仰る事ならば、なんなりと承りますよ。」
「ハハ、相変わらずおかしな子だなあ樋口君は。」
「先生…、私、もう今年で32なんです。『子』っていう年齢でもないんです…。そうなら嬉しいんですけど。」
「そうか。樋口君も大人になったもんだ。私の所にいた時は、失尾しただけで動揺してビービー泣いていたのになあ。」
宇佐美の言葉を聞いて、樋口は8年前の事を思い出した。
現在は宇佐美の勧めで独立開業しているが、樋口は元は宇佐美の事務所で働いていたのだ。
俗に言う大手企業に新卒で入社した後、直属の上司から何度となくパワハラ、セクハラを受けて退職し、引きこもりになっていた自分を拾ってくれたのは、亡くなった父の昔からの友人である宇佐美だった。できれば、直接自分の事務所に入れるのではなく、探偵の顔をきかせて何か別の仕事を紹介してくれた方がいい、と当時は思ったものだが、今ではあの時「探偵」という胡散臭い職業に就けてよかったと思っている。
一般企業の様な堅苦しさが無いし、何より余計な手順やモノを挟まずに、依頼者と1対1で対話し、1対1で感謝されるというものには、格別の悦びがある。その代償として、昼夜という概念は忘れかけてしまったし、婚期も逃してしまったが、自分の「男勝りの度胸と行動力」、「比較的整った容姿」という資質には、探偵が天職だと思った事すらある。
「先生…、私が泣いたのは最初の一回だけです。もうわかりましたから、本題に移って下さい。」
「うむ。そうだな。まず、探して欲しい人物は男性、名前は『タナカテツロウ』、特徴は、髪の毛が銀色。黒いブーツを履いている。」
「ええ。メモします。髪…銀色……、ブーツ…。」
「以上だ。」
「ええ!!それだけですか!?」
「見かけの特徴以外ならば、おそらく千葉に住んでいる。」
「あの、先生…。どれもこれもアバウト過ぎませんか?髪なんて染め直
せば黒くなるし、ブーツなんて履き替えていれば全くわかりませんよ…。
千葉県の面積、知ってますか…?」
「5156km²だ。」
「あ、知ってたんですね…。いや、そういう事ではなく…。」
「付け加えるなら、おそらく神野寺という寺の近くだと思う。」
「それもおそらく、…ですか。」
「さらに樋口君にとって有利な条件が一つある。まあ…これも推測だが。」
「さらに、の使い方が違う気がするんですが…何ですか?」
「『タナカテツロウ』は、おそらく誰かから隠れようとはしていない。言い方を変えれば、逃げようとはしていない。つまり、意図的に見かけを変えようとはしないだろうという事だ。」
「…?どういう事ですか?」
「いきさつは、少し長くなるがいいかな?」
「あまり深入りはしたくないですが…まあ、ヒントになる事なら…。」
宇佐美は樋口に事のいきさつを簡潔に説明したが、樋口は途中から「やっぱり面倒な事なのか」と、改めて自分の勘の良さに満足する事になった。
「事情はわかりました…けど、だからといって『タナカテツロウ』が『木田勇次』から隠れていないという事にはならないじゃないですか。隠れる理由が見つかっていないだけで。」
「だから、推測だと言ったろ?『そういう見方もあるよね。』くらいのものだ。」
「あるよね、って…。」
「樋口君、君は銀髪にした事はあるかい?」
「え…?ないですけど…?」
「僕も無い。普通の人はあまりしない色だよね、銀は。つまり、気まぐれで髪を銀色にしようとする人って少ないんじゃないかなあ。それ程流行色って訳でもないし。もちろん居ないとは言えないけどね。」
「…『タナカテツロウ』は、何かこだわりがあるってことですか?銀髪に?」
「こだわりとまではいかなくても、単純に銀髪が好きなのかもしれない。変わった髪の色にする人ってのは、ある程度の期間、その色のままって人が多いんだ。まあ統計を取った訳じゃないけど、そういう傾向にあると思う。」
「まあ、銀色にするには相当色を抜かなきゃいけないし、すぐに染め直したら髪も痛みますしね…。」
「ブーツにも同じ事が言える。”黒いブーツ”と言っても、鋲が付いてたりする結構ゴシック調のものらしいんだ。これも統計を取った訳じゃないけど、そういう所にこだわる人っていうのも飽きるまでは同じようなブーツを履くんじゃないかな。」
「うーん…。それはちょっと同意しかねますね。月曜日ブーツを履いて、火曜日スニーカーって人はたまに居ますよ。」
「ま、とにかくそういう傾向にあるって事だよ。ちょっと人とは違った見た目にこだわるというか。」
「はあ…。」
樋口が乗り気でない事を察知したのか、宇佐美は一つ咳払いをし、若干声を神妙にして樋口に語りかけた。
「頼むよ樋口君。難しい事を言ってるのはわかってる。何でもかんでも条件が揃っていたら、ウチの棚内君にやらせているさ。君の腕を見込んで頼んでるんだ。」
自分が慕っている人物に下手に出られれば、人間誰しも弱いものだ。また樋口としても自分を半人前扱いしていた宇佐美が、腕を見込んで、という事であれば悪い気はしない。
「…わかりました。じゃあ、調べてみます。期待に答えられるかはわかりませんが…。」
「よし、よくいってくれた樋口君。捜査期間は大体2ヶ月くらいを考えている。一応今『木田勇次の写真を添付したメールを送っておいたから。じゃあ、何かわかったら連絡を下さい。それでは。」
「あ、先生…」
電話は切れた。宇佐美の電話の切り方はいつも突然なので、樋口は大して驚きもしなかった。しかし、肝心の問題は、どうやって「タナカテツロウ」を見つけるかという事だ。
樋口は右手を顎の下に置いてしばし考えたが、何も有用な策は思いつかなかった。
「聞き込みするしかないか…。」
翌日、彼女はビジネスホテルの予約を済ませ、千葉行きの電車に飛び乗っていた。
しかし、当然というか、「タナカテツロウ」の捜索は一筋縄では行かなかった。東京ほどではないが、人の数は一人一人聞き込みをするには眩暈がするほどだし、何より神野寺は観光名所という事もあり、地元民ではない人間も多かったのだ。
しかし、彼女には探偵業を営む上で、自分で認識していない資質がもう一つあった。それは単純だが難しい、「粘り強い事」だった。彼女は自分の仕事もこなしながら、何度も千葉まで往復し、2ヶ月間諦めず聞き込みを続けた。そして、2ヶ月を少し過ぎた頃、遂に努力は実を結んだ。「タナカテツロウ」という名前で、特徴がよく似た人物を知っているという男に辿り着いたのだ。
※今度こそ続かない